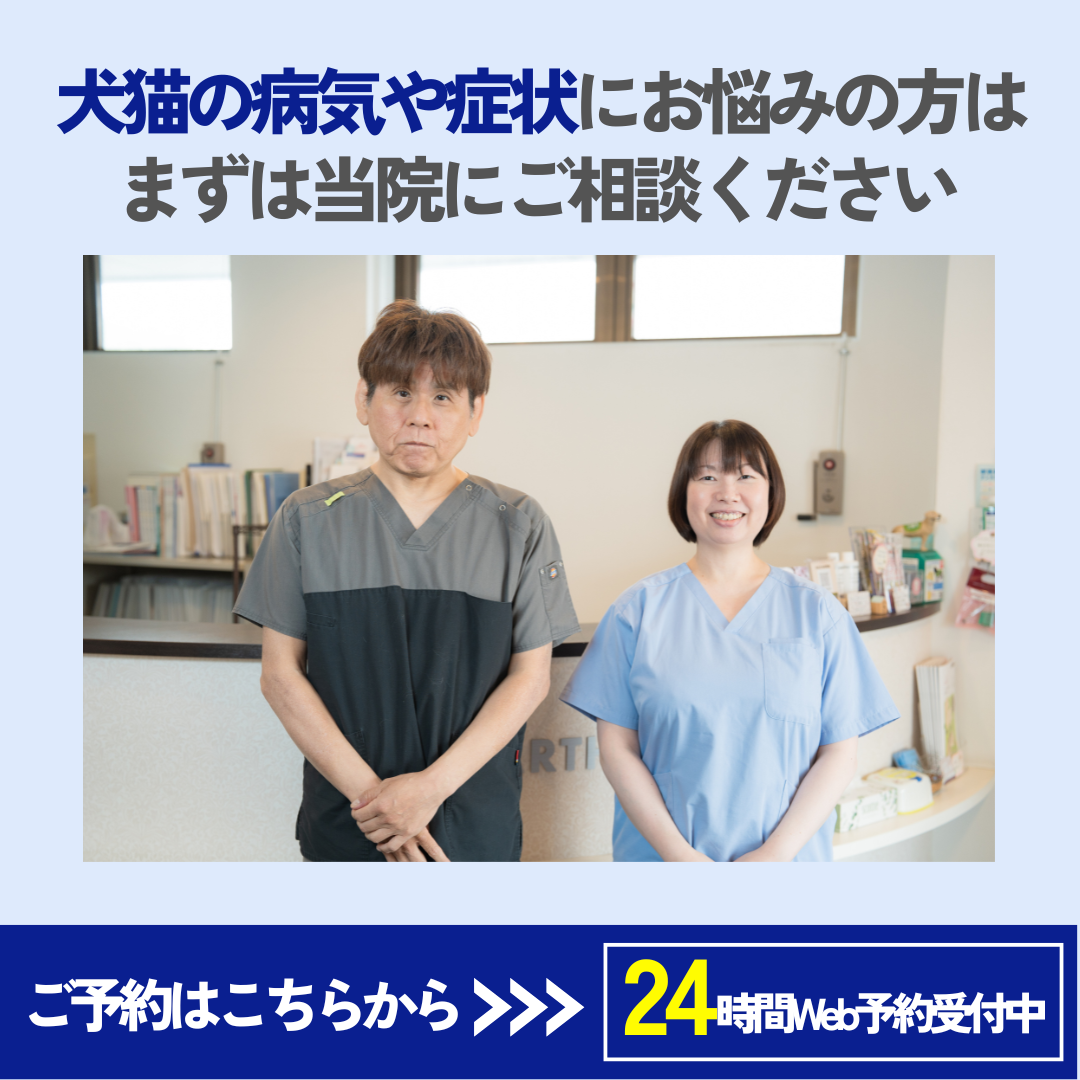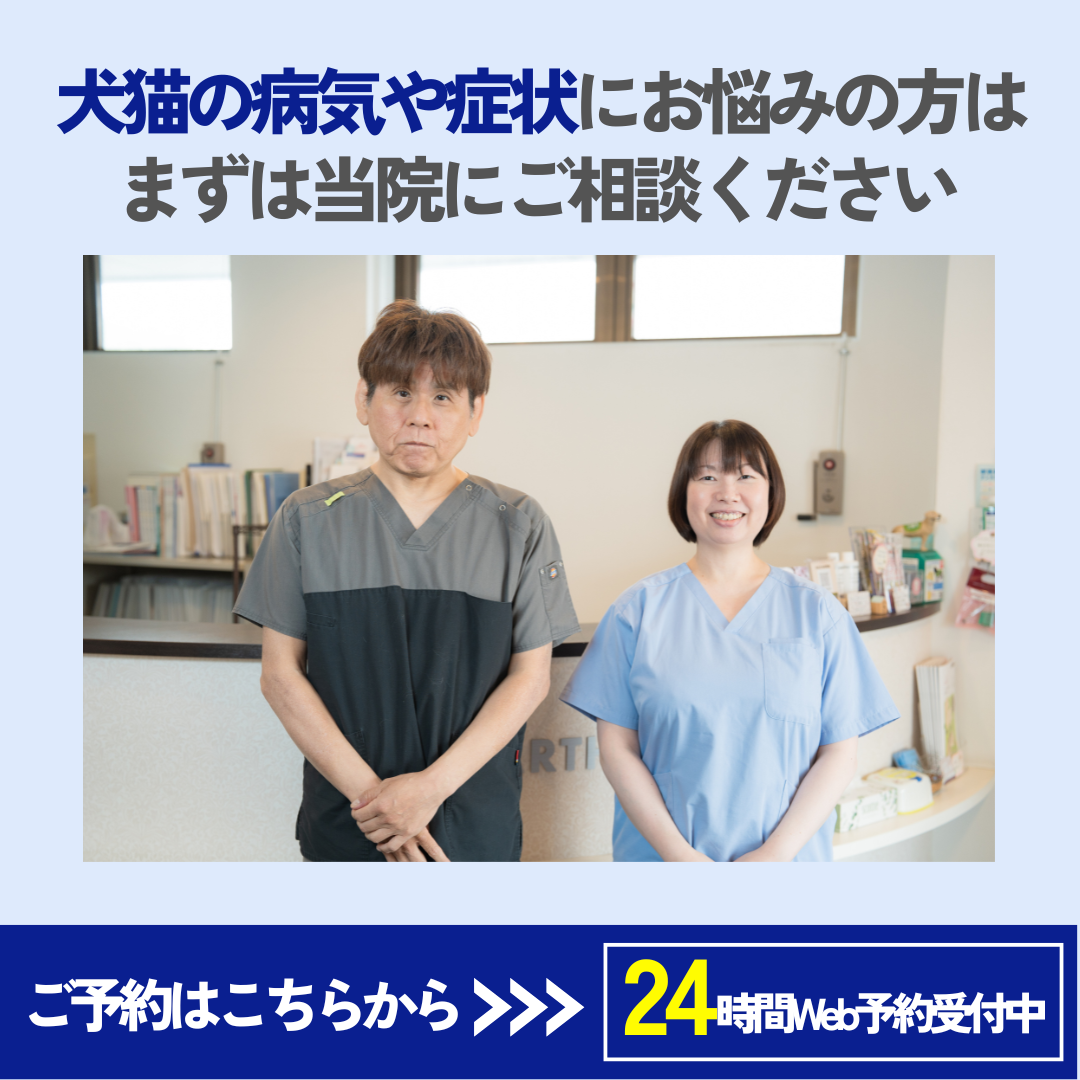【獣医師が解説】犬の膿皮症とは?原因・治療・予防法まで解説|八潮市のあーす動物病院
犬の膿皮症と受診すべきタイミングとは?
八潮市・草加市にお住まいの皆様、こんにちは。
あーす動物病院院長の横内です。
「赤いブツブツができている」
「かさぶたみたいなものが背中に…」
「痒がって皮膚をかきむしる」
このような症状が見られる場合、**「膿皮症(のうひしょう)」**という皮膚疾患の可能性があります。
皮膚トラブルの中でもよく見られる病気のひとつで、再発しやすいため継続的なケアが大切です。
今回は、犬の膿皮症についてわかりやすくご説明します。
________________________________________
症状|犬の膿皮症でよく見られるサイン
膿皮症は皮膚の浅い層に細菌が感染することで炎症が起きる皮膚病です。以下のような症状が見られます。
• 小さな赤いブツブツ(丘疹)
• 膿をもった発疹(膿疱)
• 脱毛・かさぶた・フケの増加
• 皮膚がベタベタ・においが強くなる
• 痒みや痛みで皮膚を舐めたりかきむしる
特にお腹、わきの下、内股、背中などの被毛が薄い部位に出やすい傾向があります。
________________________________________
原因|膿皮症の背景にあるもの
膿皮症は、主に常在菌であるブドウ球菌が過剰に増えることで起こります。以下のような要因が関係しています。
• アレルギー(食物・環境)
• 皮膚のバリア機能の低下(シャンプーのしすぎや乾燥など)
• ホルモン異常(甲状腺機能低下症、クッシング症候群)
• 外傷や虫刺され
• 不衛生な環境や過湿
また、免疫力の低下や他の病気が背景にあるケースもあります。
________________________________________
動物病院に行くべき目安
以下のような状態が続く場合は、悪化する前に早めにご来院ください。
• 発疹が広がってきた・膿が出てきた
• 痒みで夜も落ち着かず、ずっと舐めたりかいている
• ニオイがきつくなってきた
• 以前も同じような皮膚トラブルがあった
• 市販薬や自宅ケアでよくならない
________________________________________
治療|犬の膿皮症の基本的な治療法
膿皮症の治療は、原因と症状の程度に応じて行います。
• 抗生物質の内服(2〜4週間)
• 抗菌シャンプーや薬用シャンプーによるスキンケア
• かゆみを抑える薬(抗ヒスタミン薬・ステロイド)
• 原因疾患(アレルギー・ホルモン疾患など)がある場合はその治療
重症化している場合や再発を繰り返す場合は、培養検査や感受性検査で菌を特定して治療することもあります。
________________________________________
あーす動物病院での治療
あーす動物病院では、皮膚の状態を詳細にチェックしたうえで、以下のような治療を行います。
• 皮膚の顕微鏡検査や細菌培養検査
• 体質や生活環境に合った治療方針のご提案
• 薬用シャンプーやスキンケアの指導
• 再発しにくい皮膚づくりのための栄養指導や体質改善サポート
また、通院が難しい方にもご自宅で継続できるケア方法を丁寧にお伝えしています。
________________________________________
ご自宅での対処法
治療中や再発予防のためには、日常的なスキンケアや生活環境の見直しが効果的です。
• 週1〜2回の薬用シャンプー(獣医師の指示に従う)
• ブラッシングで皮膚を清潔に保つ
• 湿気の多い時期は除湿・通気に注意
• 舐め壊し防止にエリザベスカラーを使う場合も
• 治療中は自己判断での中断を避ける
________________________________________
予防|膿皮症を防ぐためにできること
• 定期的なシャンプーとブラッシング
• アレルギーやホルモン疾患の早期発見・コントロール
• 高温多湿の時期は皮膚を清潔・乾燥させる工夫を
• 太りすぎ・栄養バランスの偏りを防ぐ食事管理
• 定期的な健康診断と皮膚チェック
________________________________________
Q&A|よくあるご質問
Q. 膿皮症はうつりますか?
→犬同士で直接感染することはほとんどありませんが、傷口を共有しないように注意しましょう。
Q. 繰り返すのはなぜ?
→体質やアレルギー、ホルモンの乱れが背景にあると、根本から改善しないと再発を繰り返します。
Q. 自宅のシャンプーで治りますか?
→市販のシャンプーでは一時的に改善しても根本治療には不十分です。まずは獣医師にご相談を。
________________________________________
まとめ
膿皮症はよくある皮膚病である一方、再発しやすく慢性化しやすい病気でもあります。
「ただのかゆみ」「また同じ場所にできた」では済まさず、適切な治療と予防ケアが重要です。
あーす動物病院では、皮膚トラブルの根本原因を一緒に見つけ、再発しない健康な皮膚づくりを目指しています。
気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。
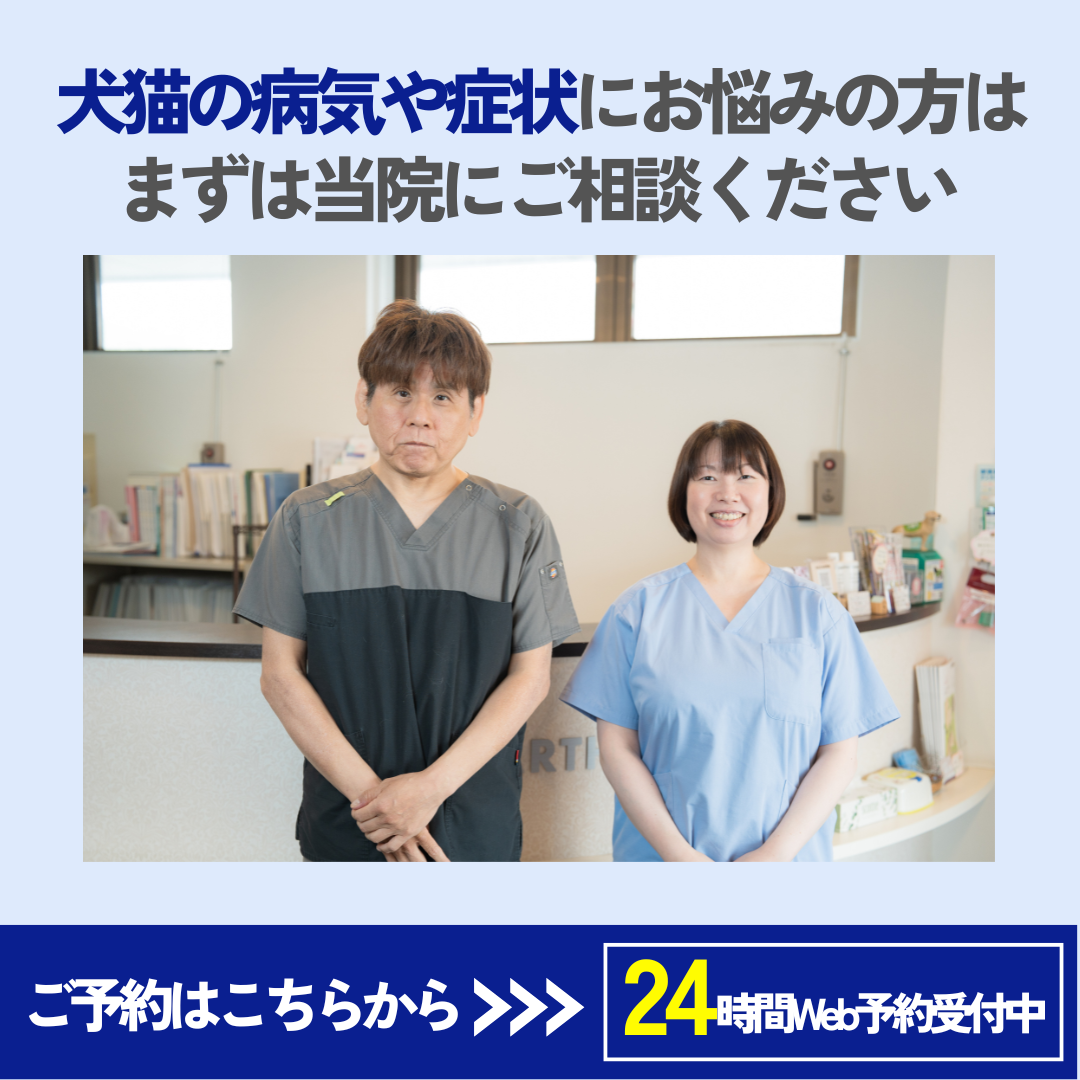
【獣医師が解説】犬のパテラ(膝蓋骨脱臼)とは?症状・原因・治療法まで|八潮市のあーす動物病院
犬のパテラ(膝蓋骨脱臼)と受診すべきタイミングとは?
八潮市・草加市にお住まいの皆様、こんにちは。
あーす動物病院院長の横内です。
「時々後ろ足を上げて歩く」
「ジャンプの後に足を引きずる」
「階段の上り下りを嫌がる」
このような様子が見られる場合、「膝蓋骨脱臼(通称:パテラ)」の可能性があります。
とくに小型犬に多く見られる整形外科の疾患で、進行すると痛みや歩行困難を引き起こすこともあります。
今回は、犬のパテラについて、症状や治療法、日常でできるケアについて解説します。
________________________________________
症状|犬のパテラで見られるサイン
• 歩いている途中に急に後ろ足を上げてケンケンする
• 足を伸ばしたりしゃがんだりした時に違和感を示す
• 膝を触ると嫌がる、または痛がる
• なんとなく足をかばっているように見える
• 座り方が不自然(足を横に流して座る)
• 症状が進むと歩行困難や関節の変形を引き起こすことも
________________________________________
原因|なぜ膝蓋骨が外れるのか?
膝のお皿(膝蓋骨)が本来の位置から内側や外側に外れてしまう状態を「膝蓋骨脱臼」といいます。
主な原因は以下のとおりです。
• 先天的な骨格の異常(遺伝性が高い)
• 成長期に膝関節の形成不全が起こる
• 滑りやすい床や高い段差の多い生活環境
• 肥満や筋力低下による関節への負担
• 外傷(転倒やジャンプによる衝撃)
________________________________________
動物病院に行くべき目安
以下のような症状が見られた場合は、早めに受診しましょう。
• 時々足を上げて歩く・ケンケン歩きがある
• 抱っこしようとすると足をかばうようにする
• ソファや階段を嫌がるようになった
• 何度も膝の脱臼を繰り返す
• シニア期になり足腰が弱ってきた
________________________________________
治療|犬のパテラの治療法は?
パテラの重症度(グレード)によって、治療法が変わります。
軽度(グレード1~2)の場合
• 体重管理(肥満は負担を増やします)
• 散歩や運動の制限
• サプリメントや消炎鎮痛剤の内服
• 室内環境の改善(滑りにくい床にする など)
• 定期的な経過観察
• 早期外科手術
重度(グレード3~4)の場合
• 外科手術(骨や靭帯を整える)
• 術後のリハビリと運動制限
• 定期的なX線チェックとフォローアップ
________________________________________
あーす動物病院での治療
当院では、以下のような対応を行っています。
• 触診やX線等によるグレード判定
• ワンちゃんの生活環境や年齢に応じた治療プランのご提案
• 手術が必要な場合は、ご家族と十分に相談の上、対応可能な専門施設への紹介
• 術後のリハビリプランやサポートも充実
初期段階での発見と適切な管理で、手術を回避できるケースもあります。気になる症状があれば早めにご相談ください。
________________________________________
ご自宅での対処法・ケアのポイント
• 滑りにくいマットを敷く(フローリングは滑りやすく危険)
• ソファや階段にステップを設置
• ジャンプや急な動作を避けるよう工夫
• 体重管理と適度な筋肉づくり(軽い散歩やマッサージ)
• 必要に応じて**サプリメント(グルコサミン・コンドロイチンなど)**を使用
________________________________________
予防|パテラを悪化させないために
• 子犬期からの適切な運動と滑りにくい環境づくり
• 段差やジャンプをなるべく避ける生活設計
• 成長期やシニア期の定期検診で早期発見
• 関節に良い食事・サプリメントの活用
• 太りすぎないよう体重管理を徹底する
________________________________________
Q&A|よくあるご質問
Q. パテラは自然に治りますか?
→自然治癒は期待できません。症状に応じた管理や治療が必要です。
Q. グレード1でも治療は必要?
→軽度でも進行を防ぐためのケアは重要です。運動制限や床対策などをご提案します。
Q. 手術が必要になるのはどんな時?
→脱臼頻度が高い・歩行困難がある・関節の変形が進んでいる場合などは、手術を検討します。
________________________________________
まとめ
犬のパテラは、早期発見と適切な管理で進行を防げる病気です。
普段の歩き方や生活の中で、少しでも「いつもと違うな」と感じたら、お早めにご相談ください。
あーす動物病院では、整形疾患にも丁寧に対応し、飼い主様と一緒に治療方針を考える診療を大切にしています。
大切なご家族が元気に歩き続けられるよう、全力でサポートいたします。
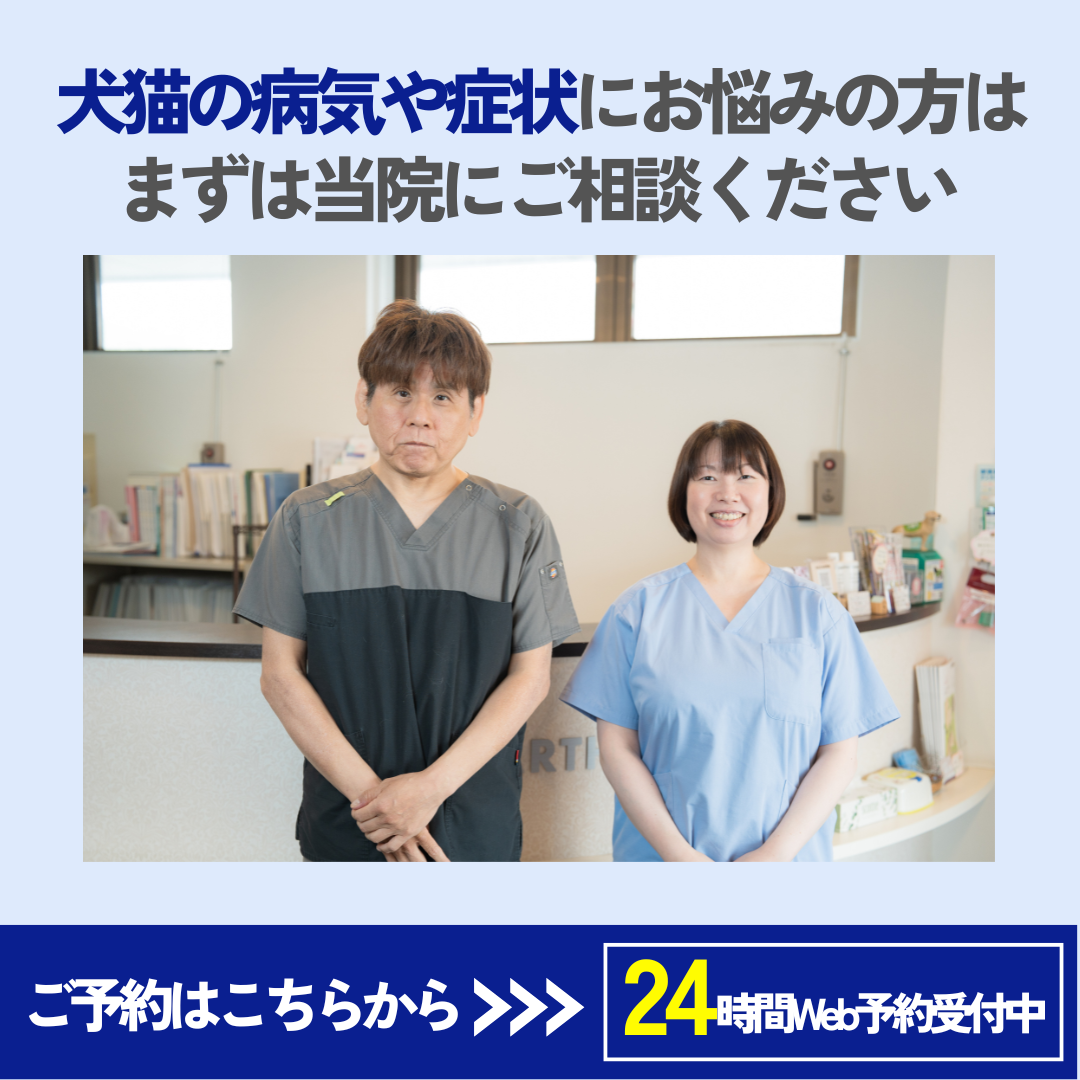
【獣医師が解説】犬に湿疹ができた?原因と治療、放置してはいけない皮膚トラブルとは|八潮市のあーす動物病院
犬の湿疹と受診すべきタイミングとは?
八潮市・草加市にお住まいの皆様、こんにちは。
あーす動物病院院長の横内です。
「お腹や脇に赤いポツポツがある」「かゆがってずっと舐めている」
そんな“湿疹”のような皮膚トラブルにお困りの飼い主様は多いのではないでしょうか。
犬の皮膚はとても敏感で、湿疹が悪化するとかゆみ・脱毛・化膿などの二次的な問題につながることもあります。
今回は、犬の湿疹の原因、受診の目安、当院での治療内容、ご自宅でできるケアについてご紹介します。
________________________________________
症状|犬の湿疹とは?
犬の湿疹とは、皮膚の表面に現れる赤み・膨らみ・かさぶた・じゅくじゅくした炎症などの総称です。
以下のような症状が見られます:
• 皮膚に赤いブツブツ・小さな発疹ができている
• 湿疹部分をしきりに舐める・かく・こする
• かさぶた・ただれ・脱毛が見られる
• じゅくじゅくして悪臭がある・ベタついている
• お腹・わき・首まわり・足先・耳などに多く見られる
________________________________________
原因|犬に湿疹ができる主な理由
湿疹は皮膚が刺激を受けたり、免疫バランスが崩れることで発生します。主な原因はこちらです。
1. アレルギー(アトピー性皮膚炎・食物アレルギー)
花粉、ハウスダスト、ダニ、特定の食材などがアレルゲンとなり、慢性的に湿疹やかゆみが続きます。
2. 外部寄生虫(ノミ・ダニ・ニキビダニなど)
特に夏場に多く、ノミアレルギー性皮膚炎や疥癬など激しいかゆみを伴う湿疹が出ることも。
3. 細菌・真菌感染(膿皮症・マラセチア皮膚炎など)
赤み、湿り気、におい、かさぶたなどが見られ、再発しやすいのが特徴です。
4. 接触性皮膚炎
散歩中に草に触れた、シャンプーや洗剤が肌に合わなかったなど、皮膚に直接触れた物が原因で湿疹が出ることがあります。
5. ホルモン異常(甲状腺機能低下症・副腎皮質機能亢進症など)
皮膚のバリア機能が落ち、繰り返す湿疹・皮膚の薄化・脱毛などが見られます。
________________________________________
動物病院に行くべき目安
以下のような場合は、早めの受診をおすすめします。
• 湿疹が数日たっても良くならない
• 広がっている・悪化している
• かゆみや脱毛が強い
• においやジュクジュクなど感染が疑われる症状がある
• 同じところに何度も繰り返す
皮膚病は見た目が似ていても原因が異なることが多いため、自己判断せず診察を受けることが大切です。
________________________________________
治療|犬の湿疹に対する治療法
湿疹の原因に応じて、以下のような治療を行います。
• 細菌感染(膿皮症):抗生物質の内服・外用薬
• マラセチア(真菌)感染:抗真菌薬・薬用シャンプー
• ノミ・ダニ:駆虫薬、皮膚の保護治療
• アレルギー:抗アレルギー薬・ステロイド・食事療法・環境改善
• ホルモン異常:血液検査のうえ、内分泌治療
________________________________________
あーす動物病院での治療
当院では、皮膚検査(細胞診・掻爬検査・ウッド灯など)や血液検査を通して、原因を特定したうえで最適な治療プランをご提案しています。
また、再発を防ぐための生活環境の見直しやスキンケアのアドバイスも丁寧に実施しています。
「まずはどんな湿疹か見てほしい」「薬を使うべきか迷っている」といったご相談もお気軽にどうぞ。
________________________________________
ご自宅での対処法
軽度の湿疹で、症状が軽い場合にはご家庭でも以下のようなケアが可能です。
• こまめなブラッシングと皮膚の観察
• 皮膚に優しい低刺激シャンプーでの洗浄(頻度は要相談)
• 湿気・乾燥のバランスを保った室内管理
• 食事内容を見直す(アレルゲン除去・皮膚ケア食)
• 舐めすぎ・こすりすぎを防ぐようエリザベスカラーなどを活用
※市販の塗り薬や人用の薬は使用しないでください。悪化することがあります。
________________________________________
予防|犬の湿疹を防ぐために
• ノミ・マダニ予防を毎月継続
• アレルゲンとの接触を避ける(掃除・空気清浄機)
• 定期的なシャンプーと皮膚の保湿ケア
• アレルギー体質の子は定期的な診察と環境整備
• 栄養バランスの取れた食事と皮膚サポートフードの活用
________________________________________
Q&A|よくあるご質問
Q. 湿疹だけで病院に行っても大丈夫ですか?
→もちろんです。湿疹は皮膚トラブルの初期症状であることが多く、早期対応が大切です。
Q. 同じ場所に湿疹が繰り返し出ます。なぜ?
→アレルギーや慢性疾患、環境要因が関係していることが多いです。一度しっかり検査することをおすすめします。
Q. 湿疹が出たらシャンプーした方がいいですか?
→症状によって異なります。悪化する場合もあるため、自己判断せず病院で相談してください。
________________________________________
まとめ
犬の湿疹は、体からの大切なSOSサインです。
かゆみ・赤み・脱毛・においなどの症状があれば、早めに原因を突き止めて対処することが愛犬の快適な生活につながります。
あーす動物病院では、原因に合わせたオーダーメイドの治療と再発予防サポートを行っています。
「いつもと違うかも」と思った時点で、お気軽にご相談ください。
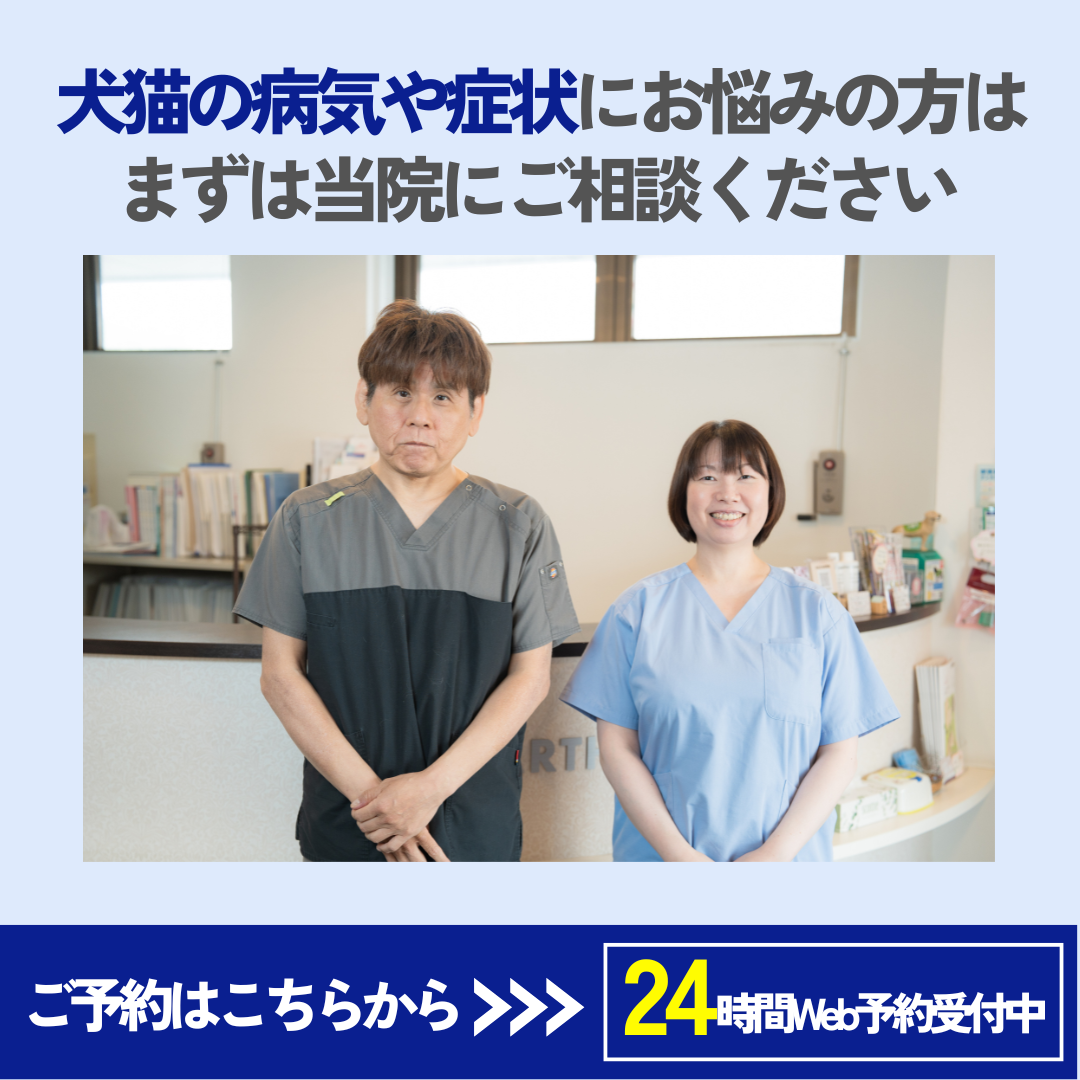
【獣医師が解説】犬の目が白い?考えられる病気と受診のタイミング|八潮市のあーす動物病院
犬の目が白い事で受診すべきタイミングとは?
八潮市・草加市にお住まいの皆様、こんにちは。
あーす動物病院院長の横内です。
「なんだか目が白っぽく濁ってきた」
「片目だけ白く見えるけど大丈夫?」
そんな“犬の目が白い”というご相談をいただくことがあります。
犬の目が白く見える場合、加齢による変化だけでなく、視力に関わる重大な病気のサインであることもあります。
今回は、犬の目が白くなる原因、受診の目安、当院での治療について詳しく解説します。
________________________________________
症状|犬の「目が白い」とはどんな状態?
「目が白い」という表現には、以下のような症状が含まれます。
• 黒目(角膜や水晶体)が白く濁っている
• 目の奥が白っぽく見える
• 片目だけ白く見える・違和感がある
• 光の反射で白くギラついて見える
• 目を細める・ぶつかりやすくなる(視力低下)
飼い主様の“なんとなく白い気がする”という違和感は、大切な気づきです。
________________________________________
原因|犬の目が白くなる主な理由
犬の目が白く見える原因はさまざまです。代表的なものをご紹介します。
1. 核硬化症(加齢による変化)
シニア犬でよく見られる現象で、水晶体が白く見えることがあります。
視力への影響はほとんどありませんが、白内障と見分けがつきにくいため要注意です。
2. 白内障
水晶体が濁って視力が低下する病気です。
高齢犬に多いですが、若齢発症や糖尿病による進行性白内障もあります。
3. 角膜潰瘍・角膜ジストロフィー
目の表面(角膜)に傷や変性が起き、白く濁る・痛みを伴う・涙や目やにが増えるといった症状が出ます。
4. 緑内障
眼圧が上がる病気で、角膜が白く濁る・視力低下・強い痛み・失明のリスクがあります。
5. ぶどう膜炎
目の中で炎症が起きる病気で、目の奥が白く見える、充血や痛みを伴うことがあります。
________________________________________
動物病院に行くべき目安
以下のような症状があれば、早めの受診をおすすめします。
• 片目だけ白くなっている
• 急に白く濁った、光に敏感、涙が多い
• 目を開けにくそうにしている、痛がるそぶりがある
• 視力が落ちたように感じる(物にぶつかる)
• 高齢犬で白内障か気になる
目の病気は、早期発見・早期治療が視力の維持にとても重要です。
________________________________________
治療|目が白いときの治療法
原因に応じて以下のような治療を行います。
• 白内障:初期は点眼薬、進行した場合は手術(紹介先にて)
• 核硬化症:治療は不要ですが、経過観察が大切
• 角膜潰瘍:抗菌点眼、点眼麻酔下で処置、重度の場合は手術
• 緑内障:眼圧を下げる点眼・内服薬、必要に応じて手術
• ぶどう膜炎:炎症を抑える内科的治療、原因疾患への対応
________________________________________
あーす動物病院での治療
当院では、スリットランプ・フルオレセイン染色検査・眼底検査などを活用し、
「白く見える原因は何か?」「視力に影響があるのか?」を丁寧に診断いたします。
必要に応じて、専門施設との連携による手術紹介も行っております。
「加齢か病気か見分けがつかない」「片目だけ濁って心配」といったご相談も、お気軽にどうぞ。
________________________________________
ご自宅での対処法
白く見える目のケアは、ご自宅でも以下のような対応が可能です。
• 目を触らないように注意する(こすらせない)
• 散歩中に顔を低くしすぎないように注意(異物混入予防)
• 清潔なコットンで涙をやさしく拭く
• 目の周りの毛を整える
• 点眼薬が処方された場合は決まった回数で正しく使用する
※**市販の目薬は使用しないようにしてください。**悪化するリスクがあります。
________________________________________
予防|目の健康を守るためにできること
• 定期的な健康診断と眼科チェック
• 歯科疾患や糖尿病のコントロール(白内障・ぶどう膜炎の予防)
• 顔をこすらない・傷つけない環境づくり
• 紫外線対策(サングラスや日差しを避ける散歩時間の工夫)
• 目に違和感があればすぐに診察へ
________________________________________
Q&A|よくあるご質問
Q. シニア犬で目が白くなってきました。白内障でしょうか?
→**核硬化症(加齢による透明度の低下)**の可能性もありますが、白内障と見分けが難しいため、検査をおすすめします。
Q. 目が白くても元気で食欲があるなら様子見でいいですか?
→**視力に関わる病気が隠れていることもあります。**できるだけ早めの診察をおすすめします。
Q. 若い犬でも白内障になりますか?
→はい。特に遺伝的要因や糖尿病などの基礎疾患がある場合、若年性白内障が発症することもあります。
________________________________________
まとめ
犬の「目が白い」という症状は、加齢による変化の場合もありますが、放置すると視力を失う病気の初期サインであることもあります。
「なんとなく違和感がある」と気づいた段階での診察が、大切な目の健康と生活の質を守る第一歩です。
あーす動物病院では、飼い主様と一緒にワンちゃんの目の変化を見守りながら、丁寧な診断と治療をご提案しています。
気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
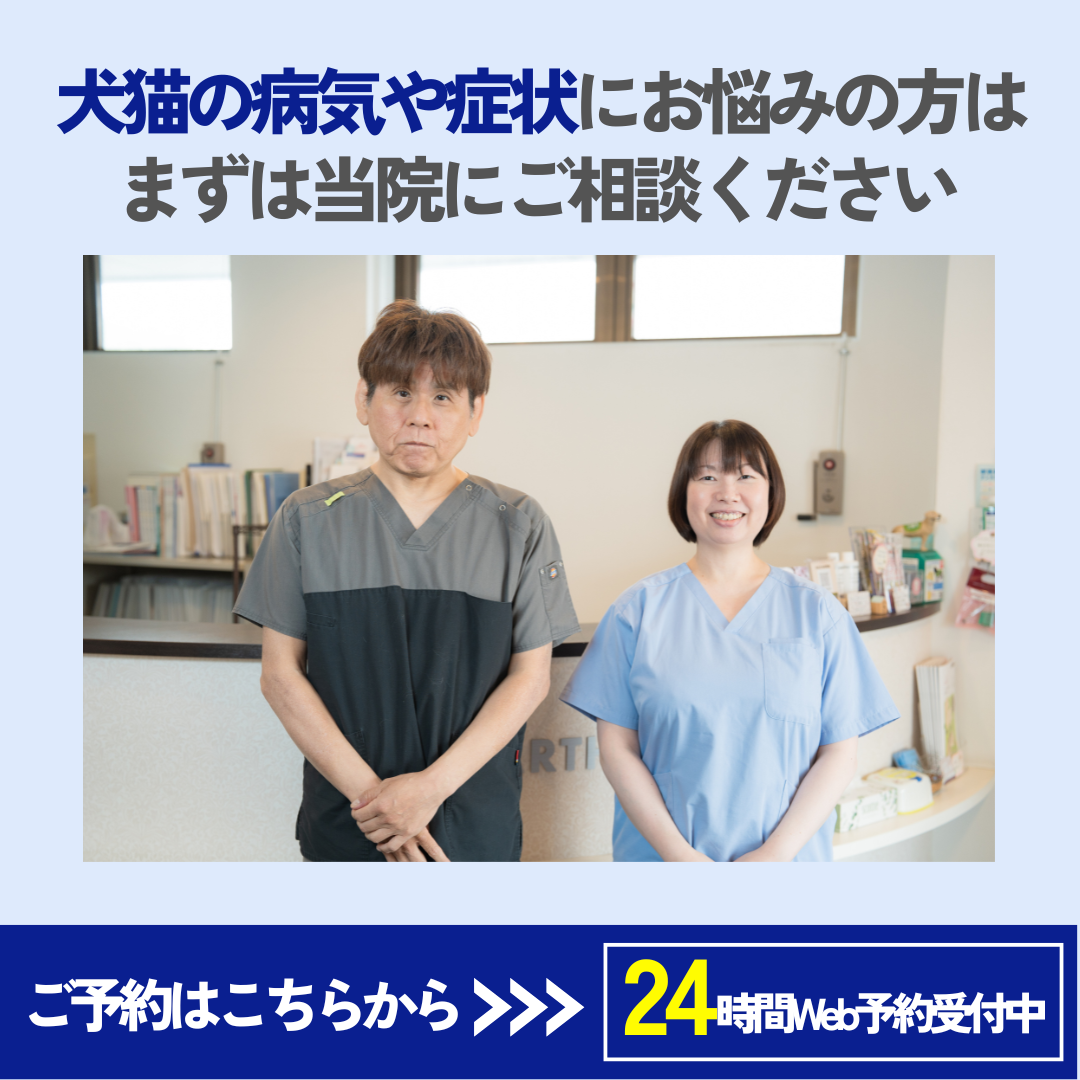
【獣医師が解説】犬の鼻血は危険?原因と対処法、受診の目安を解説|八潮市のあーす動物病院
犬の鼻血と受診すべきタイミングとは?
八潮市・草加市にお住まいの皆様、こんにちは。
あーす動物病院院長の横内です。
「急に犬の鼻から血が出てきた…」
「片側だけずっと血がにじんでいる」
そんな“犬の鼻血”に驚かれる飼い主様は多いです。
犬の鼻血は人と違って珍しい症状ですが、放っておけない病気のサインであることもあります。
今回は、犬の鼻血の原因、受診の目安、治療内容についてご紹介します。
________________________________________
症状|犬の鼻血の出方には種類があります
犬の鼻血は以下のような形で見られることがあります。
• 片側だけから血が出ている
• 両方の鼻から出血している
• サラサラとした鮮血、またはねばついた血
• 鼻をこすったときに少量の血がついている
• くしゃみと同時に出血する
• 鼻水に血が混じる
出血の量や持続時間、片側か両側かが原因を見極めるポイントになります。
________________________________________
原因|犬が鼻血を出す主な理由
犬の鼻血には以下のような原因が考えられます。
1. 鼻の中の異物(草の種、枝、ゴミなど)
散歩中に異物が鼻に入り、粘膜を傷つけて出血することがあります。
2. 外傷(ぶつけた・引っかいたなど)
遊んでいるときに鼻をぶつけたり、引っかいたりした刺激で出血することもあります。
3. 鼻腔内の腫瘍
特に片側からの持続的な鼻血やくしゃみ、鼻づまり、顔の腫れなどを伴う場合は、鼻腔腫瘍が疑われます(中高齢犬に多い)。
4. 歯のトラブル(歯根膿瘍など)
上顎の奥歯の病気が鼻腔に影響し、出血することもあります。
5. 血液の病気(血小板減少症、白血病など)
止血がうまくできない状態で、鼻血だけでなくあちこちで出血が起こる可能性があります。
6. 高血圧
高齢犬や基礎疾患がある場合、血管がもろくなって出血することも。
________________________________________
動物病院に行くべき目安
以下のような場合は、早めの受診をおすすめします。
• 片側の鼻血が何度も繰り返される
• くしゃみ・鼻水・鼻づまりを伴う
• 出血が止まらない、量が多い
• 歯ぐき・皮膚・尿などからも出血が見られる
• 元気がない・ごはんを食べない・呼吸が苦しそう
• 高齢犬や慢性疾患のある子
________________________________________
治療|犬の鼻血の原因に応じた治療法
原因に応じて、次のような治療を行います。
• 異物や外傷:内視鏡やレントゲンで確認し、必要に応じて除去や抗炎症薬を使用
• 鼻腔腫瘍:CT検査や細胞診を行い、放射線や外科手術などの治療が検討されます
• 感染症や炎症:抗生物質や抗炎症薬の投与
• 血液疾患:血液検査に基づいた内科的治療(輸血が必要なことも)
• 高血圧:降圧薬や基礎疾患の管理を行います
________________________________________
あーす動物病院での治療
当院では、鼻血の出方や併発症状をしっかり確認したうえで、必要に応じて血液検査・レントゲン・口腔内の診察・CT紹介などを組み合わせて診断を行います。
「一度だけの出血だけど気になる」「異物かどうか分からない」など、ご不安な点は遠慮なくご相談ください。
________________________________________
ご自宅での対処法
鼻血が出た場合、まずは慌てずに次のように対処してください。
• 出血側を下にして安静に寝かせる
• 鼻を強く押さえたり、こすったりしない
• 鼻のまわりを清潔なガーゼでやさしく拭き取る
• 部屋を静かに保ち、落ち着ける環境をつくる
※出血が止まらない、再発する、他の症状がある場合は必ず動物病院へ。
________________________________________
予防|鼻血を防ぐためにできること
• 散歩コースでの草や枝など異物への注意
• 高いところからの落下や衝突を避ける
• 定期的な歯科検診(歯周病・歯根膿瘍の予防)
• ワクチン・予防薬の継続で感染症を予防
• 高齢犬は定期的な血液検査で血液疾患や高血圧の早期発見を
________________________________________
Q&A|よくあるご質問
Q. 犬が鼻血を出すのはよくあることですか?
→いいえ。犬の鼻血はまれで、異常のサインである可能性が高いため、注意が必要です。
Q. 少量の鼻血なら様子見でも大丈夫?
→一度だけで止まっており、他に症状がなければ経過観察も可能ですが、繰り返す場合や他の症状があれば受診をおすすめします。
Q. 片側だけの鼻血は腫瘍のサインですか?
→必ずしもそうではありませんが、腫瘍の初期症状としてよく見られるため早期検査が重要です。
________________________________________
まとめ
犬の鼻血は珍しい症状ですが、出血の仕方や頻度によっては重篤な病気が隠れていることもあります。
「一度だけの出血だから…」と放置せず、気になる症状は早めにご相談いただくことが大切です。
あーす動物病院では、鼻血の原因を見極めたうえで、必要な検査と丁寧な説明を心がけています。
不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
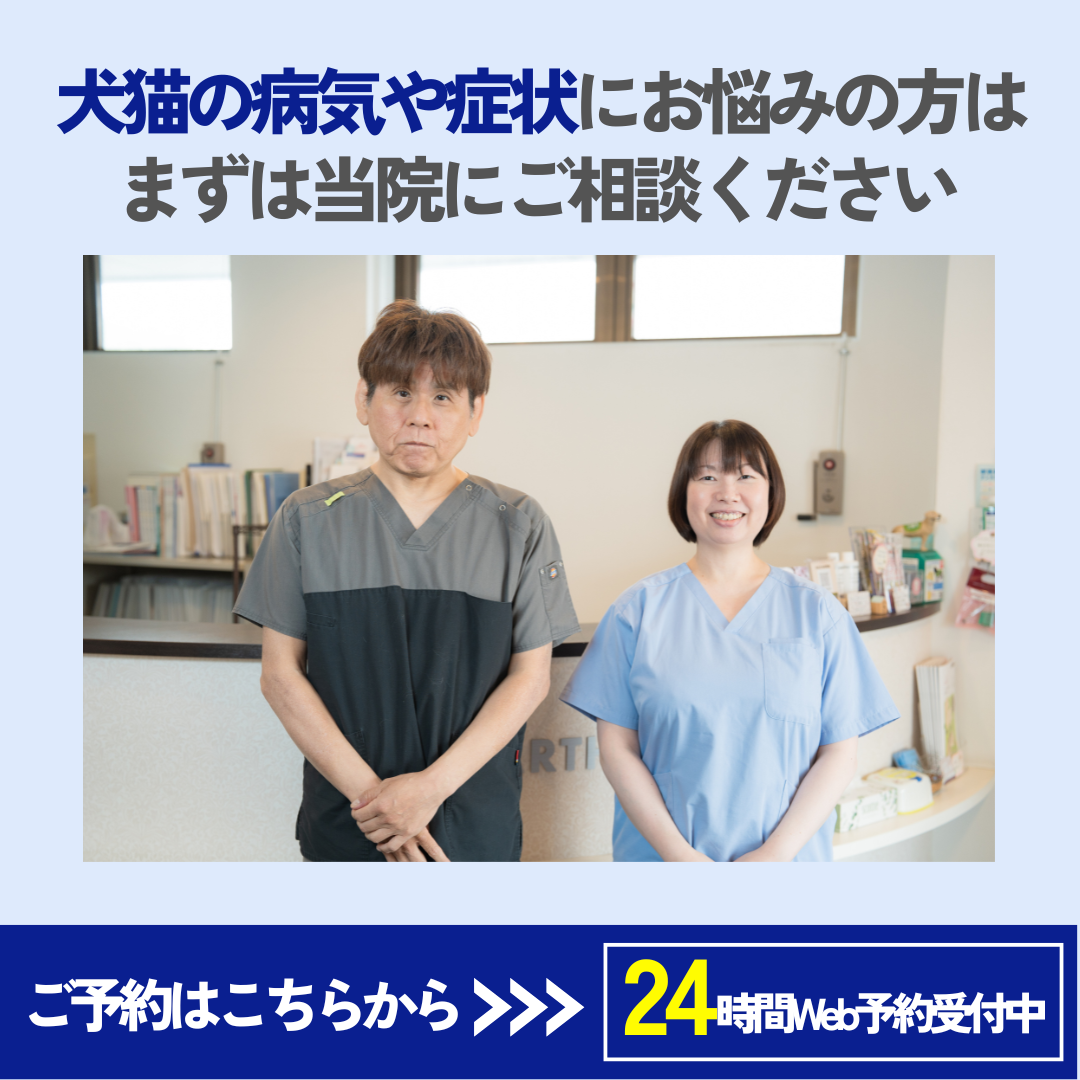
【獣医師が解説】犬の脱水症状とは?見分け方と原因、受診のタイミング|八潮市のあーす動物病院
犬の脱水症状と受診すべきタイミングとは?
八潮市・草加市にお住まいの皆様、こんにちは。
あーす動物病院院長の横内です。
「水を飲まないけど大丈夫?」
「嘔吐や下痢が続いていて、なんだかぐったりしている…」
そんなときに気をつけたいのが“脱水症状”です。
犬は体重の約60〜70%が水分で構成されており、水分が不足すると命にかかわる重篤な状態になることもあります。
今回は、犬の脱水症状の見分け方、原因、受診の目安、ご家庭での対応について解説します。
________________________________________
症状|犬の脱水症状のサインとは?
脱水症状は、軽度~重度までさまざまですが、以下のような症状が見られることがあります。
• 皮膚をつまんでもすぐ戻らない(背中や首まわり)
• 口の中が乾いている(ネバつきがある)
• 鼻が乾燥している
• 元気がなく、ぐったりしている
• 食欲がない、水も飲まない
• 目が落ちくぼんで見える
• 尿が出にくい・色が濃い
• 体温が下がる(重度の場合)
これらの症状があれば、体内の水分バランスが崩れている可能性があります。
________________________________________
原因|犬が脱水になる主な理由
犬が脱水を起こす原因は、大きく分けて以下の通りです。
1. 嘔吐・下痢
ウイルスや細菌、誤食などによる消化器症状で水分が大量に失われることがあります。
2. 発熱・感染症
体温が上がることで水分が消費されやすく、水を飲む量も減少しがちです。
3. 熱中症
高温環境に長時間いたことで体温が上がり、大量の水分と電解質が失われます。
4. 慢性疾患(腎不全・糖尿病など)
尿が多く出る病気では水分喪失が進み、脱水になりやすくなります。
5. 水を飲まない(高齢犬・口腔内の痛みなど)
飲水量が減るだけでもじわじわと脱水が進行します。
________________________________________
動物病院に行くべき目安
以下のような症状がある場合は、早急な受診が必要です。
• 皮膚をつまんでも戻らない(2秒以上)
• 水を飲まない状態が半日以上続く
• 下痢や嘔吐が続いている
• 目がうつろ・動きが鈍い・ぐったりしている
• 子犬・シニア犬・持病のある犬で体調が悪そうな場合
脱水は放置すると、ショック状態や臓器障害につながることもあります。
________________________________________
治療|犬の脱水に対する治療法
脱水の原因と程度に応じて、以下のような処置を行います。
• 軽度の脱水:経口補水・栄養管理・原因治療
• 中等度~重度の脱水:皮下点滴・静脈点滴による水分・電解質補給
• 嘔吐・下痢がある場合:制吐剤・整腸剤・抗生物質など
• 持病がある場合は基礎疾患のコントロール
点滴は体への負担や症状の緩和にとても効果的です。
________________________________________
あーす動物病院での治療
当院では、脱水の程度を身体検査・血液検査・皮膚の状態・粘膜のチェックから正確に判断し、必要に応じて皮下補液や入院点滴治療を行っています。
「水を飲まないけど病院に行くべき?」「夏の暑さで元気がない」など、
小さな不安でもお気軽にご相談ください。早期の対応が回復への近道です。
________________________________________
ご自宅での対処法
軽度の脱水や予防目的には、以下のような工夫が有効です。
• 新鮮な水をいつでも飲めるようにする
• 脱水が心配なときは、ウェットフードやスープタイプの食事に切り替える
• 電解質を含んだ動物用経口補水液(動物病院で相談の上使用)
• 高温多湿の環境ではエアコンや扇風機で室温管理を徹底
※症状があるときは自己判断せず、動物病院での診察が第一です。
________________________________________
予防|日常生活でできる脱水対策
• 飲水量を毎日チェック(飲みすぎ・飲まなすぎ両方に注意)
• 季節や運動量に応じて水分の摂取方法を工夫
• お留守番の際も複数個所に水を置く
• フードに少しぬるま湯を加える
• 高齢犬・腎疾患のある犬は定期的な健康診断で早期発見を
________________________________________
Q&A|よくあるご質問
Q. 犬の飲水量はどれくらいが目安ですか?
→健康な犬は、1日に体重1kgあたり50〜60ml程度が目安です。例えば体重5kgの犬で250〜300mlほど。
Q. 自宅でできる脱水チェックはありますか?
→はい。首の皮膚を軽くつまんで、1秒以内に戻れば正常です。それ以上かかる場合は脱水の可能性があります。
Q. ポカリスエットや人用のスポーツドリンクを飲ませても大丈夫?
→**人用の飲料は糖分や成分が犬に合わないため避けてください。**必ず動物用の補水液を使いましょう。
________________________________________
まとめ
犬の脱水症状は、放置すれば命にかかわる危険な状態です。
日頃の観察で、「水を飲まない」「ぐったりしている」「皮膚が戻らない」といったサインに早く気づけると、早期治療が可能になります。
あーす動物病院では、脱水のチェック・点滴治療・ご自宅での対策サポートまで丁寧にご対応しています。
気になる症状がある場合は、どうぞお早めにご相談ください。
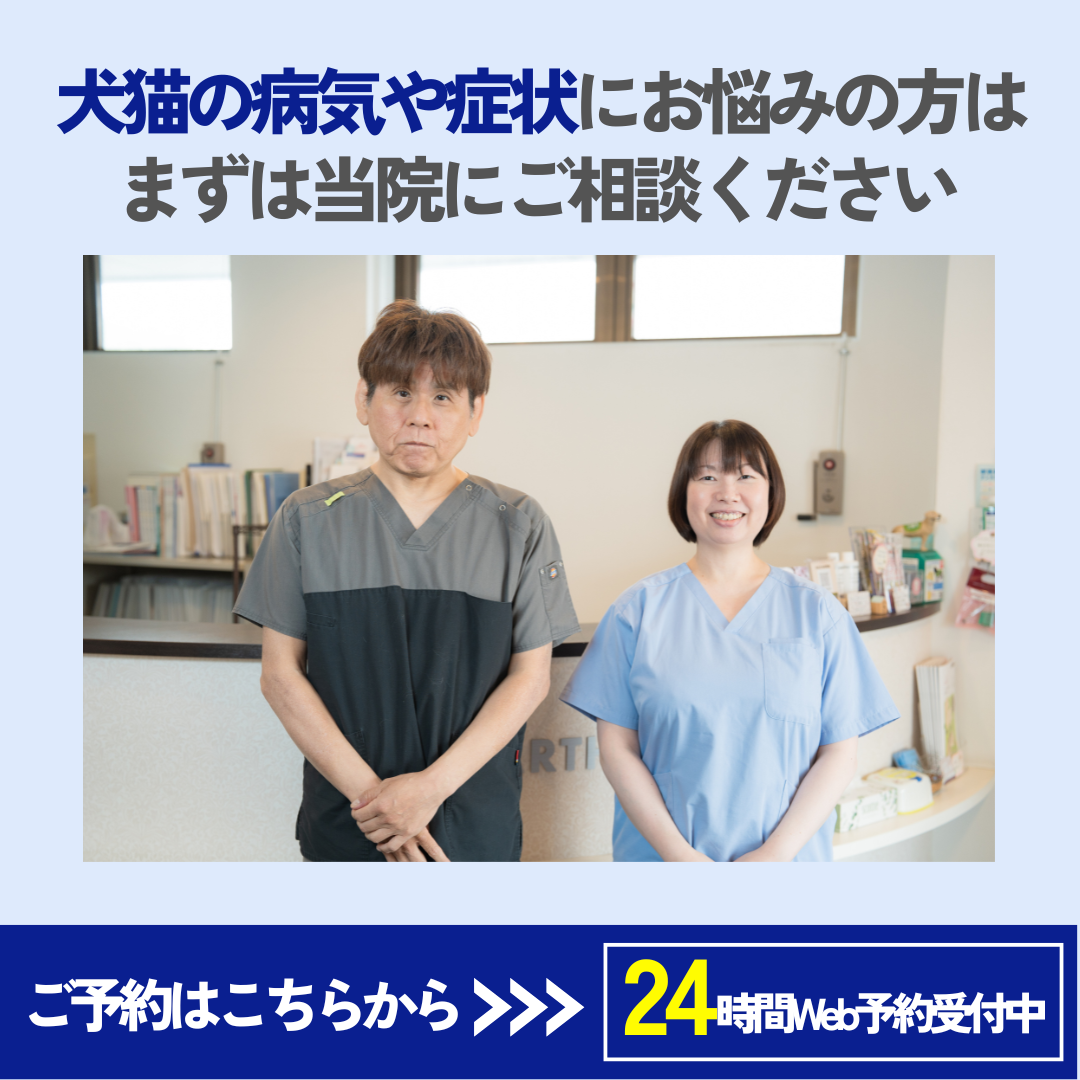
【獣医師が解説】犬にしこりができたら?考えられる原因と受診の目安|八潮市のあーす動物病院
犬のしこりと受診すべきタイミングとは?
八潮市・草加市にお住まいの皆様、こんにちは。
あーす動物病院院長の横内です。
「犬の体に触れたら、コリっとしたふくらみが…」
「まさか腫瘍じゃないかと心配で…」
そんな“しこり”に関するご相談を多くいただきます。
犬のしこりには、良性のものから早期に治療が必要なものまで幅広く存在します。
今回は、犬のしこりの原因、注意すべき特徴、動物病院を受診すべきタイミングについてご紹介します。
________________________________________
症状|犬に見られる「しこり」とは?
「しこり」とは、皮膚の下や表面にふくらみ・かたまりのような異物感がある状態を指します。
• 大きさ:米粒大〜ピンポン玉大までさまざま
• 触感:柔らかい・硬い・動く・固定されている
• 表面:つるつる・でこぼこ
• 痛み:触ると痛がる場合も
• 出血・かさぶた・毛が抜けていることも
痛みがなくても、放置せず観察が必要です。
________________________________________
原因|犬にしこりができる主な理由
しこりの原因には、以下のようなものが考えられます。
1. 脂肪腫(良性腫瘍)
高齢の犬に多く見られるやわらかく動くしこり。特に脇腹や胸部、太ももにできやすいです。
2. 皮膚の炎症や膿瘍
傷口や異物が原因で、膿がたまったり炎症が起きたりしてできる一時的なしこりです。
3. 乳腺腫瘍
避妊していないメス犬で多く、乳腺に沿って硬いしこりができることがあります。
良性と悪性の割合は半々程度といわれ、早期発見が重要です。
4. 悪性腫瘍(がん)
肥満細胞腫、軟部組織肉腫など、悪性のしこりは大きくなるスピードが速く、周囲の組織に浸潤する特徴があります。
5. ワクチンや注射の副反応
予防注射の後に一時的に腫れることがありますが、通常数日〜1週間で治まります。
________________________________________
動物病院に行くべき目安
次のようなしこりが見つかったら、早めに動物病院で診察を受けることをおすすめします。
• 急に大きくなってきた
• 表面が赤い・出血・ただれている
• 硬くて動かない、皮膚に癒着している
• 触ると痛がる・しきりに舐める
• 2週間以上消えない・大きさが変わらない
• 乳腺の近くにある(特に避妊していないメス犬)
________________________________________
治療|しこりの種類に応じた対応
しこりの治療は、**「何の細胞でできているか」**を調べることがスタートです。
• 細胞診(針でしこりの中身を採取)
• 病理検査(組織の一部を取って調べる)
そのうえで、
• 良性:経過観察または外科的切除
• 炎症・膿瘍:抗生物質や切開処置
• 悪性:外科手術・抗がん剤・放射線治療の検討
となります。
________________________________________
あーす動物病院での治療
当院では、しこりに対してまず丁寧な触診と細胞診(必要に応じて病理検査)を行い、できる限り早期の診断・治療を心がけています。
「良性か悪性か、見ただけではわからない」というケースも多いため、“見て判断せず、検査して判断する”ことを大切にしています。
気になるしこりがある方は、お早めにご相談ください。
________________________________________
ご自宅での対処法
しこりを見つけたら、以下の点を観察してメモしておきましょう。
• いつからあるか?
• 大きさ・形・位置・色の変化は?
• 触っても嫌がらないか?
• 写真で定期的に記録をとるのもおすすめです。
※自己判断で押したり潰したりしないようにしましょう。
________________________________________
予防|しこりの早期発見・早期治療のために
• 月に1回は全身を優しく撫でてチェック
• シャンプーやブラッシング時に触診を習慣に
• 乳腺腫瘍予防には若いうちの避妊手術が効果的
• 高齢犬は定期健診でしこりの早期発見を
________________________________________
Q&A|よくあるご質問
Q. しこり=がんですか?
→いいえ。犬のしこりの多くは良性ですが、見た目だけでは判断できないため検査が必要です。
Q. 小さいしこりは様子見でいいですか?
→小さくても2週間以上変化がない・大きくなるようであれば早めの診察をおすすめします。
Q. しこりは自然に治ることもありますか?
→炎症性のものは引く場合もありますが、腫瘍性のものは放置すると進行する可能性があるため、早期診断が大切です。
________________________________________
まとめ
犬のしこりは、日常のふれあいの中で飼い主様が気づける大切なサインです。
「痛がらないから大丈夫かな」と思わずに、早めに動物病院でチェックすることが、安心につながります。
あーす動物病院では、しこりの診断から治療のご相談まで丁寧にサポートしています。
ご心配なことがありましたら、いつでもお気軽にご来院ください。
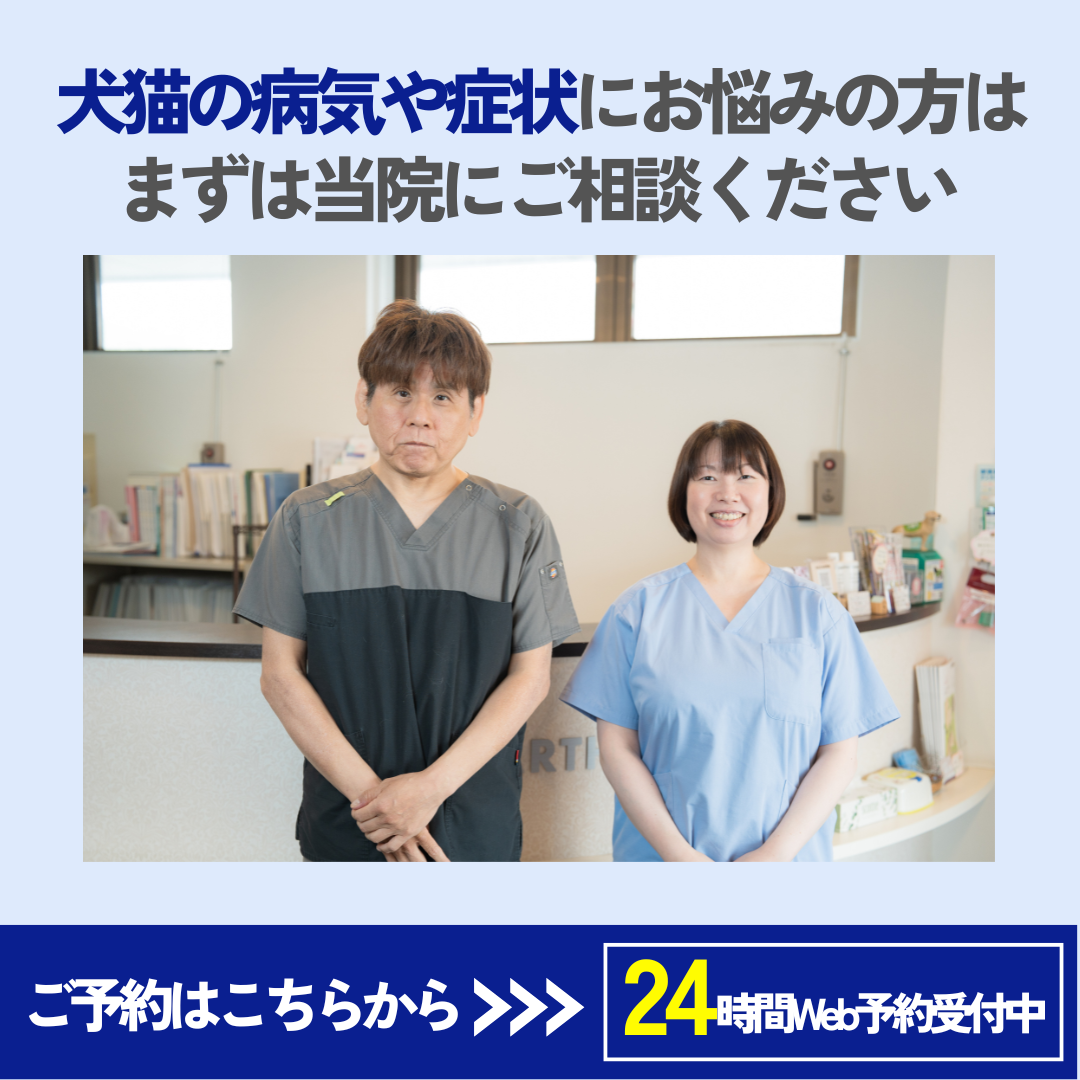
【獣医師が解説】犬の抜け毛が多いのは病気?正常との見分け方と対処法|八潮市のあーす動物病院
犬の抜け毛が多いのと受診すべきタイミングとは?
八潮市・草加市にお住まいの皆様、こんにちは。
あーす動物病院院長の横内です。
「最近抜け毛が多くて…これって換毛期?」
「触ると毛がごっそり抜けるけど大丈夫?」
そんな“抜け毛”に関するご相談は、季節の変わり目を中心によく寄せられます。
犬の毛は一定のサイクルで生え変わりますが、体調や皮膚の病気が隠れているケースもあります。
今回は、犬の抜け毛の正常な範囲と異常の見分け方、対処法についてご紹介します。
________________________________________
症状|犬の抜け毛の見え方
犬の抜け毛にはさまざまなパターンがあります。
• ブラッシング時に大量の毛が取れる
• 触っただけでごっそり毛が抜ける
• 一部の毛だけが抜けて、ハゲているように見える
• 毛が生えそろわず、地肌が透けて見える
• 毛と一緒にフケや赤み、かさぶたがある
• 同じ場所を舐めたり掻いたりして、毛が抜ける
全身的か、局所的か、皮膚の状態に異常があるかが重要な判断ポイントになります。
________________________________________
原因|犬の抜け毛が多くなる主な理由
1. 換毛期(春・秋)による自然な抜け毛
特にダブルコートの犬種(柴犬、ポメラニアン、ラブラドールなど)では、季節の変わり目に大量に毛が抜けるのが自然な現象です。
2. アレルギー性皮膚炎
食物や環境アレルゲンに反応してかゆみ・炎症・脱毛を引き起こすことがあります。
3. ノミやダニなどの寄生虫
激しいかゆみや掻き壊しで、局所的に毛が抜ける・赤くなる症状が現れます。
4. ホルモンの病気(甲状腺機能低下症、クッシング症候群など)
左右対称の脱毛、皮膚が黒ずむ・毛の再生が遅いといった特徴があります。
5. ストレス・舐め壊し
過剰なグルーミングや舐めすぎにより、手足・お腹まわりに部分的な脱毛が見られることがあります。
________________________________________
動物病院に行くべき目安
以下のような場合は、自然な抜け毛とは異なります。
病気が隠れている可能性もあるため、早めの受診をおすすめします。
• 地肌が見えるほど毛が抜けている
• フケ・赤み・かさぶた・ニオイなど皮膚の異常がある
• 左右対称に脱毛している
• 部分的にハゲている・しこりがある
• 毛が生えてこない・全体的に薄くなってきた
• かゆみが強く、舐めたり掻いたりが止まらない
________________________________________
治療|犬の抜け毛に対する治療法
抜け毛の原因に応じて、以下のような対応を行います。
• 寄生虫の駆除:ノミ・ダニ予防薬の使用
• アレルギー対応:食事療法・抗アレルギー薬・スキンケア
• ホルモン疾患の治療:内服薬でホルモンバランスを調整
• 感染症治療:抗生物質・抗真菌薬の投与
• スキンケア:保湿シャンプーやサプリメントの活用
• ストレス対策:生活環境の見直しや行動療法
________________________________________
あーす動物病院での治療
当院では、抜け毛のパターンと皮膚の状態をしっかり観察し、必要に応じて皮膚検査・血液検査・ホルモン検査などを行います。
「換毛期との違いがわからない」「他の病気が隠れていないか心配」という場合でも、丁寧にご説明しながら治療方針をご提案いたします。
________________________________________
ご自宅での対処法
軽度の抜け毛や換毛期には、以下のような対応が有効です。
• 毎日のブラッシングで抜け毛を取り除く(皮膚への刺激にもなる)
• 部屋の湿度を適度に保つ(乾燥は皮膚トラブルの原因に)
• シャンプーの頻度は月1~2回程度、皮膚に合ったものを使用
• 食事の見直し(オメガ3脂肪酸などを含むフード)
• ストレスを減らす(お留守番時間、遊びの質を見直す)
________________________________________
予防|抜け毛を最小限に抑えるために
• 毎日のスキンシップで毛の変化・皮膚の異常に早く気づく
• 定期的なノミ・ダニ予防
• 年1回以上の健康診断でホルモンバランスや皮膚の状態をチェック
• シニア犬には皮膚・毛質に配慮した食事とケアを
________________________________________
Q&A|よくあるご質問
Q. 抜け毛が多いけど、食欲も元気もあります。病気でしょうか?
→換毛期の可能性もありますが、皮膚の赤み・かゆみ・ニオイがあれば一度診察をおすすめします。
Q. 抜け毛がひどくて部屋が毛だらけです。対策はありますか?
→こまめなブラッシング・換毛期専用ブラシの活用がおすすめです。また、皮膚トラブルが原因の抜け毛なら治療で改善します。
Q. 一部だけ毛が抜けて地肌が見えています。自然に治りますか?
→**病気やホルモンの乱れが原因の場合、自然には改善しません。**早めに受診してください。
________________________________________
まとめ
犬の抜け毛は、自然なものと病的なものの見極めが難しい症状です。
「なんとなく多い気がする」「前より薄くなってきたかも」といった日常の違和感が、早期発見につながることもあります。
あーす動物病院では、皮膚や被毛の健康も全身状態の一部として丁寧に診察しています。
ご不安なことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。